〒447-0065 愛知県碧南市久沓町4丁目55番地
受付時間 | 9:00~20:00 ※不定休(土日祝日も対応) |
|---|
アクセス | 名鉄三河線北新川駅 徒歩5分 駐車場:有 |
|---|
独立系FPが語る暦年贈与の注意点
(一般に言われていることは本当か)

あちこちのサイトで暦年贈与のやり方について解説記事を目にします。金銭消費貸借契約だとか贈与契約書がどうとか「それさえあれば大丈夫」みたいな書き方をしているものをよく見かけます。
元税理士事務所職員の目線で見ると、とっても危ないことをお勧めしているものが多いように感じます。
そこで、元税理士事務所職員の独立系FPとして今までいろんな税理士の先生方に教わってきたことを踏まえつつ、後から後悔しない暦年贈与の活用方法とその準備についてお話していこうと思います。
独立系FPが語る暦年贈与の注意点
様々なサイトで言われている贈与の仕方について、思うところをお話します。
- 贈与税がかかる場合
- 基礎控除と受贈額の考え方
- 定期金の贈与
- 金銭消費貸借契約(両親からお金を借りる)
- 一緒に考えてくれる専門家を味方につける
贈与とは

贈与とは何でしょう?今回は思わぬ申告漏れや脱税行為をしてしまわないように、税務の面から考えたいと思います。税務的には「1月1日から12月31日までの間に」「個人から贈与により財産を取得したとき」に「取得した財産の価額に対して」贈与税がかかります。
国税庁HP:No.4402 贈与税がかかる場合
仮に個人ではなく法人から何かをもらった時は、贈与税ではなく所得税がかかります。(給与所得や雑所得等になります)
問題はこの贈与税がかかる場合について考えるとき、意外と盲点が多いということです。
「えっ、それって贈与なの?」というケースが意外と多いのです。
例えば、グレーなものも含めると
「子供の代わりに住宅ローンを払ってあげた」「子供名義の生命保険の保険料を払ってあげた」
「不動産の所有権保存登記の時の共有割合が出資割合と違う」
「今まで自分が払っていた生命保険の名義を子供に変えた」
「子供に車を買ってあげた、もしくは車をあげた」「成人式のお祝いに1000万円包んだ」
「共有名義の土地の税金をすべて負担してもらっている」「親戚に安く土地を譲ってもらった」
「お金を貸した(ある時払いの催促なし、出世払い、無利息など)」などなど
なかには国税庁のHPを見ると例示されているものもあります。
「そんなの贈与だと思っていなかった」なんてものはありませんか?
基礎控除と受贈額の考え方

ここで贈与税の課税の仕組みを見ていきましょう。
贈与税には基礎控除という制度があります。「毎年いろいろ貰った中から110万円までは贈与税を課税しません」というものです。110万円という金額の根拠はあまりないと考えていいでしょう。昔は違う金額でした。
贈与税の課税の対象は「この1年間(1/1~12/31)に贈与されたもの全部」です。
Aさんから50万円・Bさんから100万円もらっていたとしたら、150万円(100万円+50万円)が対象(受贈額:もらった金額)になります。
一番多くくれた人でも110万円以下だから申告・納税の必要はないというのは間違いです。
受贈額は基本的に現金はもらった金額で、物の場合「時価」あるいは「相続税評価額」という法律で決められた方法で計算した金額になります。詳しく細かいことの説明は省きますが、低額譲渡(適正な価額以下の金額で譲り受けた一定の場合は、差額について受贈したとみなされる)などの決まりもあります。特に、土地家屋や車両などを贈与された場合や、安く譲ってもらった場合には税理士に相談しましょう。
因みに、申告して税金を納めなくてはならないのは「もらった人(受贈者)」です。あげた人のことは贈与者といいます。
さらに、受贈者(もらった人)が税を納めないときには贈与者(あげた人)に納税義務が発生するケースもあります。(第2次納税義務者といいます)
必要な時にはきちんと申告、納税したいものですね。
定期金の贈与

贈与の中には、いくつか注意しなくてはならない贈与の形があります。上で紹介した低額譲渡などもそうですが、定期金の贈与というものがあります。
基礎控除が110万円あるからと、他のサイトなどでも相続対策と称して毎年110万円ずつ暦年贈与することを勧めるケースが多く見受けられますが、実はこの考え方は少々危険を伴います。いくつか理解して抑えておくべきポイントがありますので、その点についてご紹介します。
・ケース1:年末に110万円+年始に110万円贈与する。贈与契約書1枚。
どういうことかというと、例えば12/25に110万円贈与します。年明けには課税期間が変わることから1/10にもう110万円贈与します。これを贈与契約書を作ればいいからと、1枚の贈与契約書で「12/25に110万円、翌年1/10に110万円贈与する」と決めてしまうものです。
よく考えてみましょう。この契約書は「12/25に合わせて220万円を贈与する契約」を結んでいますね。税務署から問い合わせがあった時に、この贈与契約書を出すことは危険だと思います。
正しくは「12/25と1/10と別々に贈与契約を結ぶ」です。
・ケース2:毎年誕生日に110万円贈与する。贈与契約書1枚。
どういうことかというと、毎年毎年110万円ずつ贈与することを契約してしまうことです。1年に基礎控除が110万円なのだから構わないと思うかもしれませんが、大きな間違いに発展する可能性を秘めています。
税務の世界には定期金の贈与という考え方があります。毎年同じ金額を贈与する契約という考え方があるのです。例えば「10年間毎年110万円渡します。」という契約になるわけですが、これは契約を結んだ時点で「110万円を10年間毎年もらう契約」として計算されることになります。「10年間もらうことに対して、契約時点で」課税するという考え方になります。これも贈与契約を結ぶ際に要注意です。キチンと専門家に相談のうえで、契約書を作成する必要があります。
国税庁HP:No.4402 贈与税がかかる場合
相談する相手が税務に詳しくないとこういった部分を見落として、後々問題となるケースが考えられます。契約書の作成段階から充分な検討が必要です。
金銭消費貸借契約(両親からお金を借りる)

住宅の購入の際など両親から資金を出してもらったり両親と共有名義にすることや、両親からお金を借りるということを安易に提案するケースが見受けられます。
ここではお金を借りる際の、贈与税に絡んだ注意点をご紹介します。
特に親子間で金銭のやり取りをする際には、契約書なんて水臭いとか・出世払いでいいよとか・利息なんか取る気はないなどといったやり取りになりがちです。
しかし、そもそも借金をしようというのに契約書(金銭消費貸借)がないとか、利息が付かないとか、返済期限がないなんて都合の良い話は通りません。
仮に親子間であってもお金を借りるのであればきちんとした契約書と借金としての体裁と事実が伴っていなくてはいけません。
・面倒くさがらずに内容の伴った金銭消費貸借契約書を作成する
・銀行口座を通じたお金のやり取りをして記録を残す
・少なくとも利息の支払いをする(銀行口座を通してお金を動かして記録を残す)
この3点は必須です。
国税庁のHPにも「出世払いやある時払いの催促なしは贈与とみなします。」といった記載があります。
国税庁HP:No.4420 親から金銭を借りた場合
一緒に考えてくれる専門家を味方につける

贈与税は自分で思っている以上に身近な税金です。
我々の生活の中で思わぬところで顔を出してきます。
しかも、税率は他の税金と比べても高いものです。
何か大きくお金を動かす時や、慣れない資産の動きなどある際には専門家に相談できると安心です。
税金について専門とするのは税理士です。契約書の作成なら司法書士です。専門家の先生に時間をとってもらうとどれだけお金がかかるかわからなくて怖いとか、敷居が高くて…などという方は当事務所にご相談ください。
一般論として回答できるケースについては、その場でお調べしてお答えします。
無料相談の範囲で収まってしまえば御代も発生しません。
専門的な計算や判断を要すると当事務所で判断すれば税理士に回答を求めるか、直接ご紹介します。
2023/8/21
2024/7/26更新
2025/8/14更新
2025/9/12更新
贈与に関することでお悩みなら
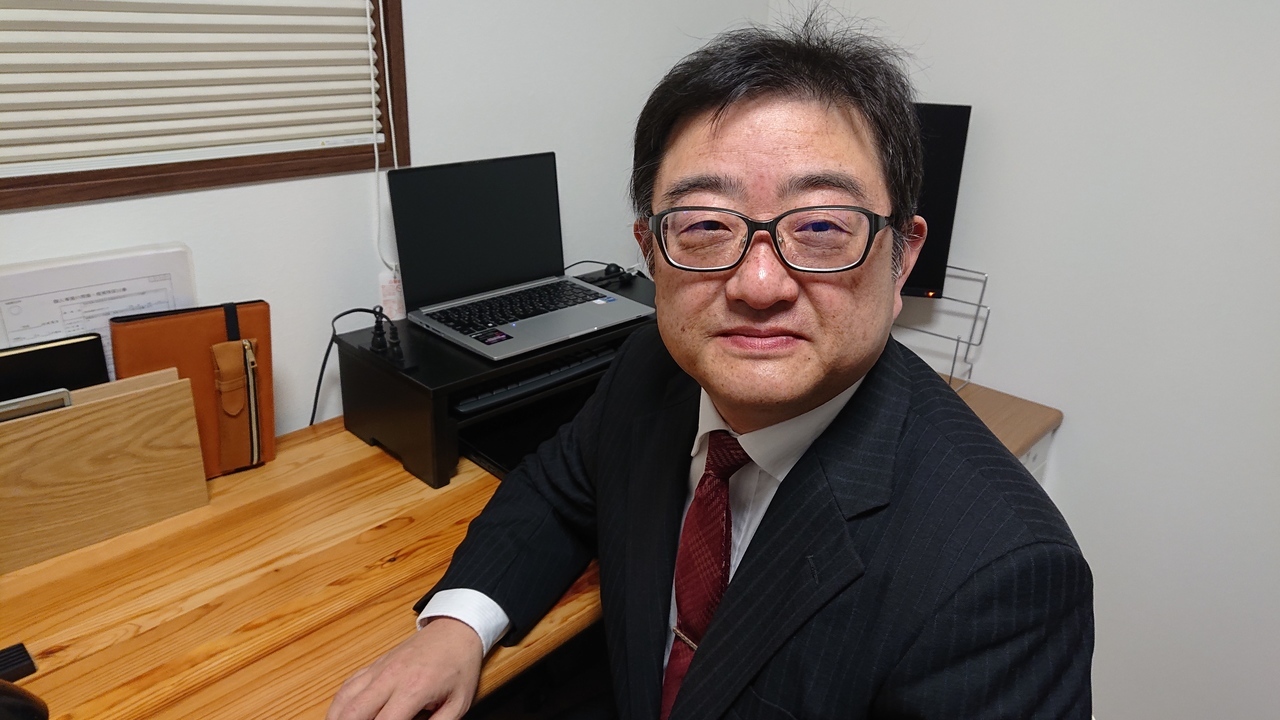
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
独立系FPとしての立場から、暦年贈与についての注意点について考えてみました。
今、いろんな紹介サイトで住宅ローンやその他の相談に回答しているものが見受けられます。ただ、色々なコラム等見ていても読んでいてこちらが怖くなってしまうような、中途半端な内容のものが多いのは事実です。
後で嫌な思いをしないためにも、是非、一度当事務所にご相談ください。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~20:00
※不定休(土日祝日も対応)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
かわすみFP事務所

住所
〒447-0065
愛知県碧南市久沓町
4丁目55番地
アクセス
名鉄三河線北新川駅 徒歩5分
駐車場:有
受付時間
9:00~20:00
定休日
不定休(土日祝日も対応)


