〒447-0065 愛知県碧南市久沓町4丁目55番地
受付時間 | 9:00~20:00 ※不定休(土日祝日も対応) |
|---|
アクセス | 名鉄三河線北新川駅 徒歩5分 駐車場:有 |
|---|
相続対策講座
第7回 相続税対策は必要か

第5回までは2つの相続対策でいうところの「相続手続対策」についてお話をしてきました。
前回の第6回でもう一つの相続対策である「相続税対策」についてご紹介しました。
ここからは「相続税対策」に関して多少具体的な内容について話を進めます。
今回お話しするのは、そもそも相続税の対策は必要なのかどうか。「税金を納めるのは憲法に定められた国民の義務なんだから、どだい対策とはけしからん」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。
相続対策講座
第7回 相続税対策は必要か
相続財産はどのくらいあったら相続税がかかるのか。
相続税対策が必要なのはどういった場合か。などお話します。
- 相続税が出る人
- 基礎控除の計算の仕方
- 資産と負債の計算の仕方
- 特例の適用と申告義務
- 相続税対策がなぜ必要か
相続税が出る人

相続税の対策のお話をするからには、相続税が出るかどうか。相続税の申告と納税の必要があるかどうかについてまずい考えなくてはいけません。
相続税は簡単に言うと
相続財産(資産)-相続財産(負債)-基礎控除>0
この状態の方は申告と納税が必要になります。
相続財産(資産・負債)の考え方は税務の世界特有の解釈方法があったりするので、ここでは詳しく解説しません。
もっと簡単に説明すると
「借金を返していくらかでも残る人は、その金額が基礎控除より大きければ申告の必要がある」と考えるとわかりやすいかもしれません。
基礎控除については次の章でご説明します。
参考:国税庁HP タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合
基礎控除の計算方法
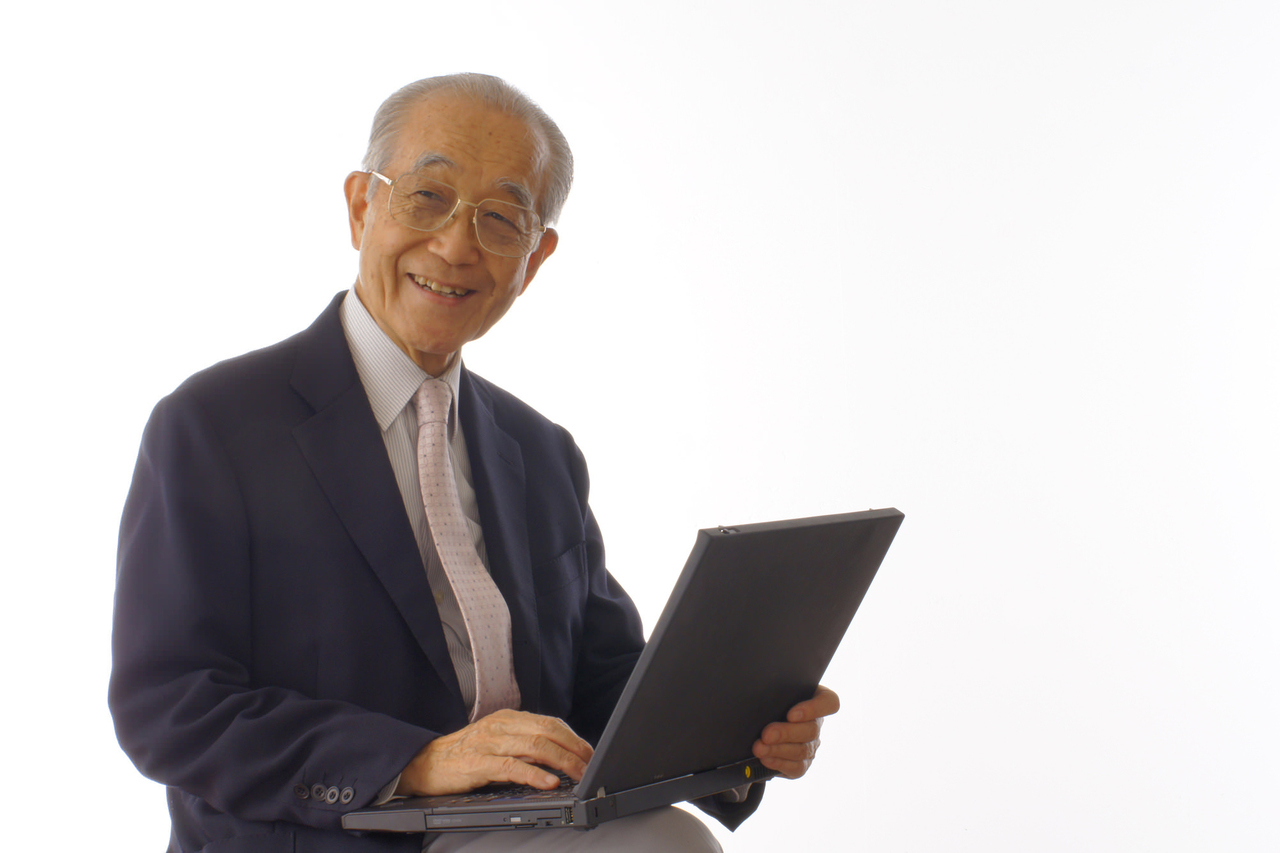
基礎控除の計算方法は
3000万円+600万円×法定相続人の数 となります。
法定相続人とは民法に定められた相続人です。法的に少なくともこの人たちは相続人(遺産を受け取る権利のある人)ですよ。と定めている人の人数になります。
基本的には配偶者・子供・尊属(父母及び祖父母)・兄弟の順で相続すべき順位と割合が決まっています。配偶者は常に法定相続人となり、子供がいれば配偶者と子供。子供がいなければ配偶者と尊属。尊属もいなければ兄弟といった具合です。
夫婦と子供二人の4人世帯で仮にお父さんが亡くなったとすると、お母さんと子供二人が法定相続人となります。この場合の基礎控除の額は
3000万円+600万円×3人(お母さん、子供二人)=4800万円 という計算になります。
資産と負債の計算の仕方

資産については第5回資産の評価でも解説しましたので、ここでは少し細かい部分について解説します。
相続財産の中には一般的なイメージと少し違う考え方や捉え方をするものがあります。
例えば「みなし相続財産」主なものは生命保険の死亡保険金です。
被相続人(亡くなった方)が契約して保険料も払っていた保険について、死亡保険金の受取人は(本人は亡くなった状態で支払われるものなので)本人以外の人が受取人指定されることになります。よくあるのは独身の方なら両親とか、結婚していれば配偶者などといった具合です。被相続人が亡くなる時点では、まだ死亡保険金は発生していません。死亡することによって死亡保険金受取人に受け取る権利が発生します。
よく考えてみましょう。これ、被相続人の財産でしょうか?
この生命保険による死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれるもので、相続税の計算上は相続財産に含まれます。一見違うように見えるかもしれないけど、相続財産とみなします。というものです。
ただし、受け取る権利は死亡保険金受取人にあるため死亡保険金受取人に固有の財産とみなされます。つまり遺産分割の際に遺産分割協議の対象とはならず、手続きさえすれば死亡保険金は死亡保険金受取人が全額を直接受け取ることになります。
一方で、相続財産とならない資産もあります。例えば、仏壇やお墓など祭祀に関するもの。お葬式で受け取る香典も相続財産にはなりません。
負債についても独特の考え方があります。葬儀に関する費用は被相続人が支払うわけではなく遺族がその内容について決めて支払うものです。ただ、相続税の計算の上では負債として扱います。戒名や読経に対して支払うお布施もそうです。一方で、負債扱いとなるのは葬儀に関するもののみで七日参り、百日法要などは対象となりません。(初七日法要については葬儀と同時に済ませてしまうものについては葬儀費用に含めてよいようです)
参考:国税庁HP No.4105 相続税がかかる財産 No.4108 相続税がかからない財産
特例の適用と申告義務

では、相続財産の合計から負債を引いたものが正(プラス)であれば必ず相続税の納付が必要となるのでしょうか。
そうとも限りません。
相続税の計算に置いていくつかの特例が存在します。
例えば、
相続人とともに資産の形成に貢献してきた配偶者にとって有利となるような配慮をするもの。(配偶者の税額の軽減)
障害のある方や未成年に配慮するもの。(障害者の税額控除)(未成年者の税額控除)
相続人の事業を存続させるためのもの。(事業承継税制法人版・個人版、農地の納税猶予など)
相続人と同じ住居に住んでいた人を配慮するもの。(小規模宅地の特例)
こういったいくつかの特例があります。(リンク先は国税庁ホームページ)
詳しくは国税庁のホームページで相続税の特例についてみてみましょう。
(特例適用の条件や事前準備が必要なものもあります)
これらの特例を適用することで相続税の納税額が0円となる場合もあります。
ただし、これらの特例を適用するにはその条件を満たしていることを示す資料と、その旨を記載した申告書の提出が必要となります。そうなると相続税の納付はしなくても良いですが、期日までに申告書を作成して提出する手続きは必要という場合もありうることになります。
実際の適用に関する可否判断は個別に専門家(税理士等)を交えて判断することになります。
相続税対策がなぜ必要か
では、相続税対策は必要なのでしょうか?
相続税は相続財産として何らかの経済価値のあるものを相続した際に課税されます。
しかも負の遺産(負債)を差し引いて、且つ葬儀費用なども差し引いた残りに対して課税されます。
つまり、何らかのプラスの財産があった時にその中から税金を納付することになります。
通常であれば納税に困ることはないように思えます。
相続財産のすべてが現金であれば・・・
ここが問題なのです。
相続財産の大半が土地家屋であったり株式、とくに未上場株式などであったりすると、
納税のための現金が確保できない可能性があります。
時には納税のために借入をする必要が出てくるケースもあります。
さらに相続税は個人が直面する各種税金の中でも、金額が多くなる傾向のある税金です。
残された人たちが納税資金に困らないように対処しておくことも、相続税対策の大きな側面です。
2024/5/8公開
2024/5/16加筆
2024/7/18更新
2025/8/12更新
相続対策でお悩みなら

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
今まで何件かの相続(争族)に立ち会ってきた独立系FPとしての目線で、相続対策の一側面についてお話しました。
このあたりからの内容は個人で判断すると非常に危険を伴う内容になってきますので、必ず税理士等の専門家に相談していただきたいと思います。当事務所では具体的な判断や税額計算は税理士法に抵触しかねないため提供できないのですが、事前に必要な下準備をしたうえで信頼できる専門家をご紹介することができます。
相続に際してこんなことを聞いておきたいというものがありましたら、遠慮なくご相談ください。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~20:00
※不定休(土日祝日も対応)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
かわすみFP事務所

住所
〒447-0065
愛知県碧南市久沓町
4丁目55番地
アクセス
名鉄三河線北新川駅 徒歩5分
駐車場:有
受付時間
9:00~20:00
定休日
不定休(土日祝日も対応)


